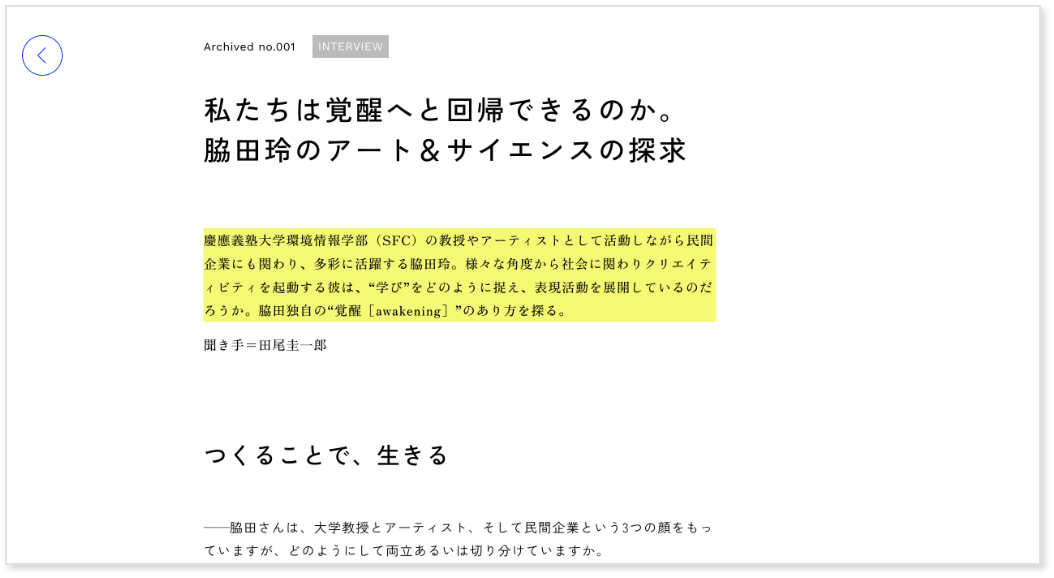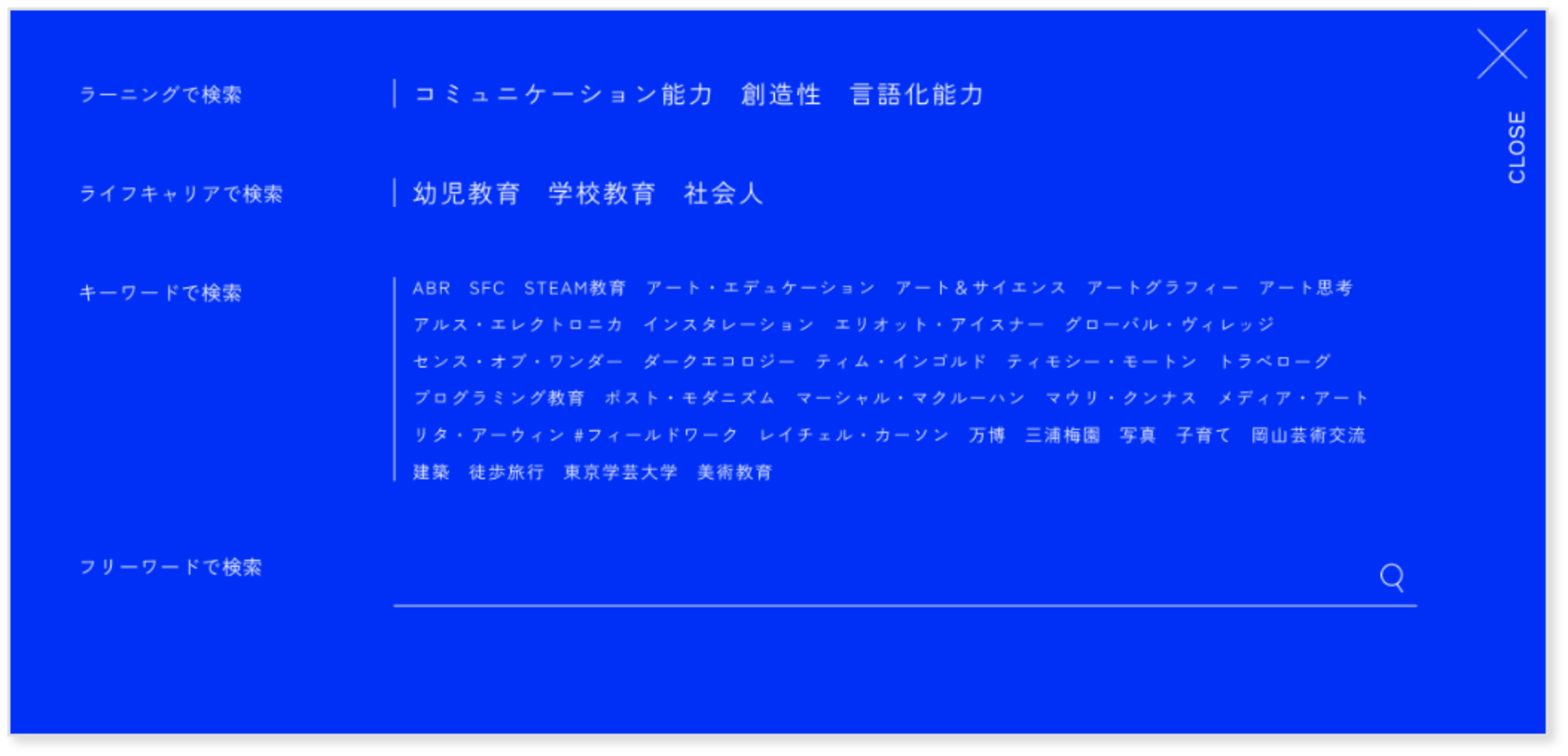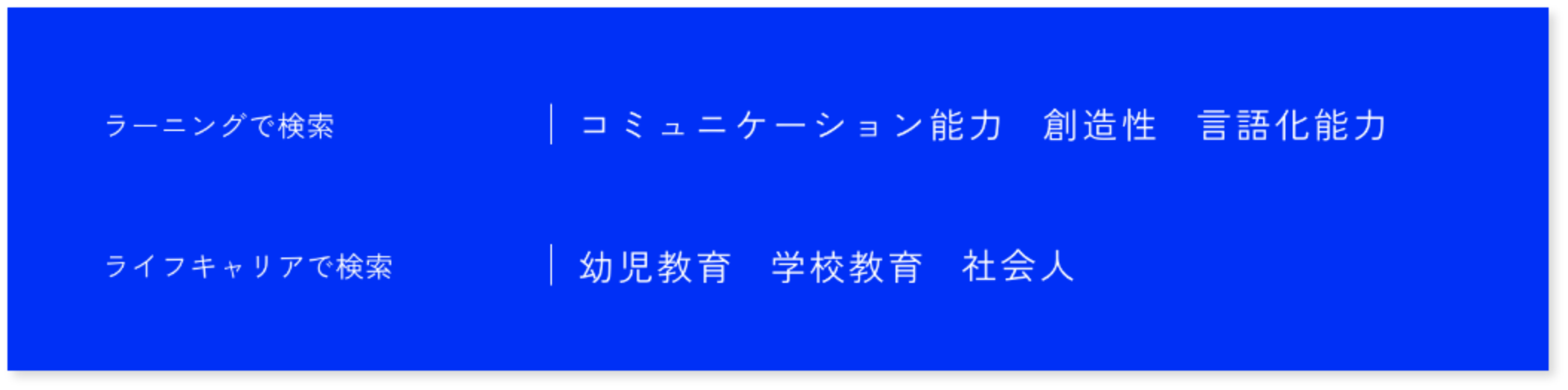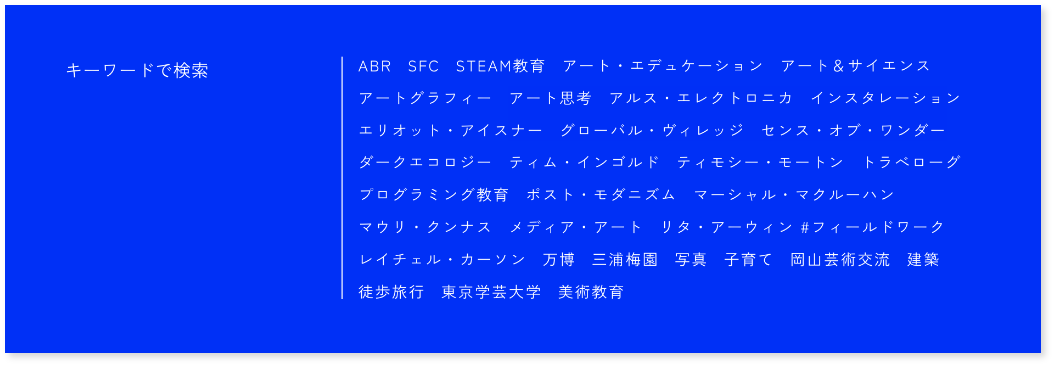現代的映像の温度:後編
ジャン・ルーシュの「共有された人類学」から辿り直す
「零度」の現代から
前回の記事で私は映像に対する「零度の態度」を提示した。ここでロラン・バルト(*1)の「零度のエクリチュール」を想起する人もいるかもしれない。
(詩の言葉では)言葉が意味を部分的に規定する冠詞を奪われ、一種の中立的ゼロ状態に引き下げられるのだが、過去において使われたものと未来において使われる可能性のあるもの、すべての特殊な意味を同時に含んで膨れあがり、生きた状態でいられる。(*2)
しかしバルトはこうしたエクリチュール(*3)に期待を寄せながら、それが容易に実現しないことも予期していた。言葉が時空間を乗り越え、生き生きと変化し、私たちの生の仕方に合わせて発生することは、同時に「意味不能」になる可能性すら抱えている。詩はそうしたギリギリの落下直前の場所でどうにか作者の意思と解釈者の可能性と作品それ自体の命とを繋ぎ止めた「零度の」言葉なのである。
現代の私たちにとっての映像もまた、こうした水準で捉えうるものなのだとすれば、私たちの「詩学」は映像人類学がすでに示してくれているかもしれない。理論的な背景からほんの少しだけ「詩学」を辿り直してみよう。
「共有された人類学」と切断
映像人類学、と口に出して発音するとき、頭に付せられた「映像」が私たちにダイナミックな動きの連続やロードムービー、映画、そしてドキュメンタリーなどを思い起こさせる。事実、映像人類学を学んだひとはその後のキャリアで映像制作や広告に携わるなど、何かしらの記録と伝達にかかわる進路へ向かうこともあるという。
ところで、英語圏ではこの「映像人類学」に対応する分野は「Visual anthropology」と呼ばれている。そのまま直訳すれば「視覚人類学」となるだろうか。むしろこちらのほうが、今回取り上げる映像人類学的ワークショップの内容にふさわしいかもしれない。確かに私たちが扱ったものは映像であるのだけれど、その態度はむしろ「記録と伝達」を超えて、そこに〈視聴する・解釈する・またおのれの生活に戻る〉というなにか文学的な営みの予感さえ感じられたのだ。
日本語圏での映像人類学のイントロダクションとしては、私には『映像人類学(シネ・アンスロポロジー)―人類学の新たな実践へ』(*4)という本が思い浮かぶ。このタイトルに付された「シネ:Ciné」はジャン・ルーシュ[Jean Rouch(*5)]による論文「Ciné-Ethnography(シネ・エスノグラフィー:映像民族誌)」(2003)を参照したものだ。そこで「Ciné」は次のように登場する。
カメラが捉える現実としての「映画の真実:Film truth」を、人間が直面する現実と取り違えてはならない。フィルムに刻印された「映画の真実」は、人間のそれとは決定的に異なる。したがって、日常生活を映画的ヴィジョンに置き換えることは、現実をシネ=リアリティ(ciné-reality)に、そしてシネ=トゥルース(ciné-truth)に、ついにはシネ=ヴィジョン(ciné-vision)に変換することである。こうしたヴィジョンは、再帰的な「参与カメラ」と、それまで撮影していた主体との、詩的かつ直接的なコミュニケーションの結果でなければならない。(*6)
そう、ルーシュははじめから現実そのものを記録しようとは考えていない。主体がカメラをどう扱うのか、そしてカメラが主体にどう反応するのか……。今では、自動露出や録音、スローモーション機能などがスマホに盛り込まれ、ほとんど自然な行為として“撮影”が可能だ。この現代的で自然な撮影はルーシュの述べる「詩的かつ直接的なコミュニケーション」にどう影響しているのだろうか。
さて、こうしたシネ=ヴィジョンの行き着く先、ルーシュによる映像人類学は、はたしてshared-anthropology共有された人類学になるのだという。

『ある夏の記録』(1961)から
この「share:共有する」という言葉はとても興味深い語源を有している。かつては「scearu:切ること」であり、さらに源流を辿ると、ゲルマン祖語でのskaro、skerana、そして印欧語根のsker−に行き着くのだが、これらはいずれも「切る」という意味を有するのだという。おおよそ似た発音で、同じ語源を有しているshearは「裁ちバサミ」であることからも、その根底に「切断」があることが認められるだろう。
何かを共有するためには、何かを切り分けなければいけない……というやや教訓めいたことをここから読み取ってみるとしても、あながち間違ってはいないだろう。私たちは私たちの感じたことすべてを他者に共有できるわけではない。何かを伝えるために私たちは、経験を細かく分節化し、ときおり、メタファーを挟み込んだりしながら、主観と客観とを織り交ぜて話す。そうやって伝達された情報は、本来の情報そのものというより、話し手の色が付された現実=詩になる。切り分けられた部分が全体を代表して、その切断が「あなたらしさ」に取って代わる(*7)。
さて、どのような形・経路であれ、映像人類学が「視覚」をベースとしながら、そこでなにかの伝達と共有をその主題としているのだとして、やはり興味を惹かれるのはそこで発生する「詩学」である。たんなる切断と共有、出来事の伝達であれば、そこに詩学を介在させる必然性は薄い。そこで映像人類学が芽生えさせる詩学のかすかな匂いを辿ることで、情報の濁流でいまを生きる私たちの目が必要とする詩について、考えることができるのではないか。
根拠のない信頼
思い返してみれば、わたしたちの日常は切断され、共有された映像に溢れている。唐突な導入、30秒ほどのショート動画、巻き返され、見飛ばされる数々の断片。あるいは誰かの謝罪会見や号泣、痛ましい事件、エログロ、ほとんど意味のないように思える私的な記録、安売りされていく感動や、どこかのアフリカ系の人々がたどたどしい日本語で読み上げる祝福。
こうした断片だらけの現実から何かを拾い上げ、心を動かしたり、怒ったり、落ち込んだりする私たちの日常は、つねにすでに、映像人類学者であるといってよいのかもしれない。映像人類学者たる視座によって、現実を捉え返す。現実は目の前にあるのだけれど、私たちの伸ばす手と、純然たる目によって、現実は形を変え、私たちに「根拠のない信頼」の素材を提供してくれる。
そこから「根拠のない信頼」の素材を切り取り、編集し、組み替え、壊し、再び組み立て直す作業を通じ、なにかを共有できるようにするのは、私たちの内奥にある〈Ciné=詩学〉に依っている。最後にドゥルーズの『シネマ』から断片的に引用してみよう。
・・・つまり、問題は、言葉の手前で、あるいは彼方で、世界への信頼を再発見すること、取り戻すことである・・・
・・・それなら微妙な出口とはどんなものか。別の世界を信じることではなく、人間と世界の絆、愛あるいは生を信じること、不可能なことを信じ、それでも思考されることしかできない思考不可能なものを信じるようにして、それらを信じることだ。「可能なものをいくばくか、さもなければ息がつまってしまう」。この信頼こそが、不条理なものによって、不条理なものの力で、思考されないものを思考に固有の力能にするのだ・・・
・・・確かなのは、信じるということは、別の世界を信じるということではなく、改造された世界を信じるということでもないということである。それはただ単純に、身体を信じることである。言説を身体にもどすことである。そしてそのためには、言説以前の、言葉以前の、事物が名づけられる前の身体に到達しなくてはならない・・・(*8)
言葉の手前で、映像を解釈する口や耳や目を手放して、現地の匂いや湿度を感じるおのれの感覚器官の彼方で、映像を信じること。それが、映像人類学的な思考法なのではないか。そしてそれが、この「息がつまってしまう」ような世界で生きることを可能にしてくれる。インターネット上であらゆる事実も現実も想像も虚構もすべてが混淆に私たちに突き刺さってくる世界で、映像を見ること。
さきの引用でドゥルーズが「不条理なもの」と示したのは、おそらくジャン・ジュネ、ウジェーヌ・イヨネスコ、そしてサミュエル・ベケットらによる「不条理演劇」を受けての表現と思われるが(*9) 、ここからやや脱線して……切断して……ポーランドにて「不条理演劇」の先駆けを試みたと言われるスタニスワフ・イグナツィ・ヴィトキェーヴィチ(俗にヴィトカツィ)(*10)を軽く参照してみよう。
ヴィトカツィは演劇以外にも写真作品を多く残しているのだが、この写真作品の「顔」は純然たる「顔」そのものとして現れている。こめかみから顎までを示すぎりぎりの部位でタイト・トリミングされ、それ以外の状況をひたすら切除した写真群。その顔は顔以外のなにものをも示さない、極度な顔への集中がゆえに、次第に顔らしさが瓦解していくように見える。表情の温度は低く、私たちはこの撮られた顔の前で、どうすればよいかもわからなくなってくる。ドゥルーズが示した〈事物が名づけられる前の身体で、微妙な出口を通り抜け、信じること〉は、こうした顔なのではないか、と思う。

1911年から12年にかけての写真作品。いずれもMaciej Szymanowiczの論文から
私たちを見つめ返す顔捉え返す現実、素材その先にある詩的な声。不条理演劇は反文学的だというより、その「しかえす」態度によって文学的たりえているのではないか。同様に、あの日私が感じた映像人類学もまた、「しかえす根拠のない直感」によって、現実をタイトに見つめているのである。私たちがこの絶え間ない情報に溢れた現実のなかで、出来事をほとんど無作為に選び取るように。ヴィトカツィの写真が示した胡乱な目は、私たちの目ではあるのだけれど、私たちはこの目からも「根拠のない信頼」をつかまえて、どうにかして現実を生き抜いていくよりほかない。SNS上に溢れる顔、顔、顔、もはや本当の顔なのかAIが作った顔なのかも判然としない無数の顔から、どうにかコミュニケーションを、人類学を、生み出していくのだ。
むすびにかえて
私が感じた映像人類学的思考法が、どこまで映像人類学的で、民族誌的なのか、という疑問は数多く残っている。しかし、確実に……これもまた根拠のない直感で……映像を見つめ、現実を捉え返す態度は、現代の私たちの生き抜く実践に近い匂いがする。泣くことも叫ぶこともなく、ただひたすらに情報の濁流のなかで「おねがい、何かを信じさせて」と見つめているのだ。
橋爪の論文から引いた「他人の土地」に住まうことの不安をきっかけとした「自分たちの土地」への帰還という背景も、情報過多の現代に住まう私たちの、遣り切れなさ、焦燥感、薄く息の詰まった感覚、そうした印象に重なってくる。
ヴィトカツィの『狂人と尼僧』という戯曲作品のなかで、ヴァルプルクはこう述べる。
ヴァルプルク:大きな工場の、しかし管理し制御する者のいない機械室を想像してみてもらいたい。そこのメーター類の針は全部、とうの昔に赤い線を超えてしまっているが、あいかわらず狂ったように動きつづける機械室を。
シスター・アンナ:(ずっと掌を組み合わせて聞いている)でもどうして今、現代では、何もかもがそんな風な終わり方をするのですか?
ヴァルプルク:昔は「表現形式の飽くなき探究」だとか、藝術における倒錯だとかいうようなことは言わなかった。人間の生は、魂のない自動機械の無目的な運動じゃなかった。社会は機械じゃなかった。あったのは苦悩する家畜たちがひしめきあいながら固まった群れと、その上に咲いた欲情、権力、創作、そして残虐の見事な花だ。でもそんな話はどうでもいい。人生について僕らの人生について話そう(…)。
シスター・アンナ:神様、神様、神様……(*11)
ヴィトカツィのこの戯曲は1923年の作品である。『狂人と尼僧』からちょうど100年経ってなお、残虐の見事な花は枯れていない気もする。あらゆるところで私たちを監視し、コントロールする機械に囲まれたいま、私たちが必要とし、行使する「詩学」が「根拠のない信頼」なのだとすれば、「僕らの人生」もまた、根拠のない(あってもなくてもいい)ものだろうか? そうではない、と思うのならば、わずかばかりでも「詩学」を紡ぎ出してみよう。その詩から生まれてくる温度が、ほんの少しでも「零度」を温めうるかもしれない。
waxogawa/小川楽生
キュレーター、研究者。2001年石川県生まれ。先天性両耳重度難聴という背景から、「ことばを話す」という行為は当たり前の能力ではない、という立場を採り、人文学的視座からキュレーション業務を行っている。キュレーションのテーマは「言語による贈与論の超越」。現在は日本橋馬喰町のスペースNEORT++(ネオルトツー)にてキュレーターとして活動。