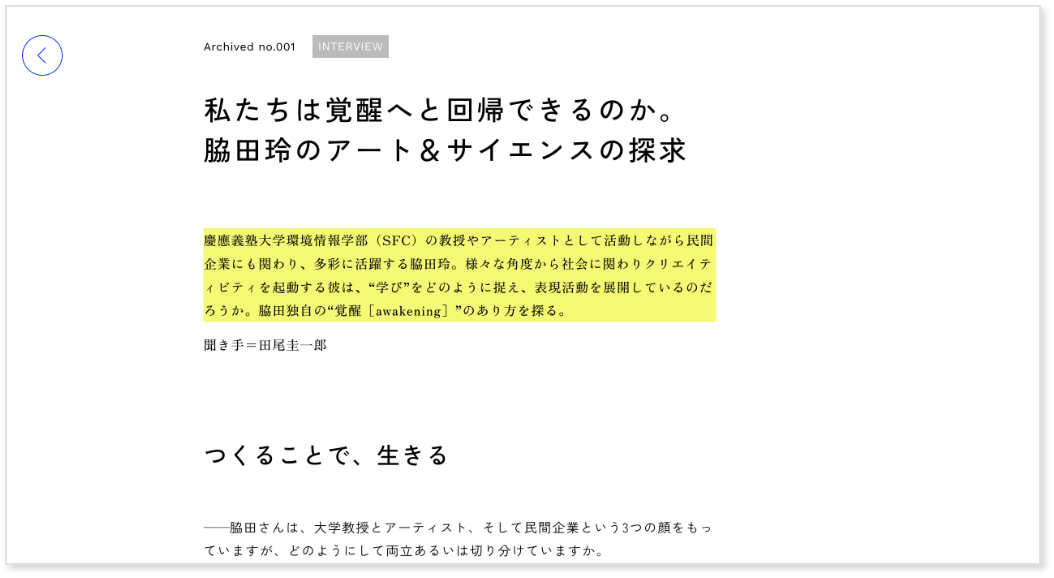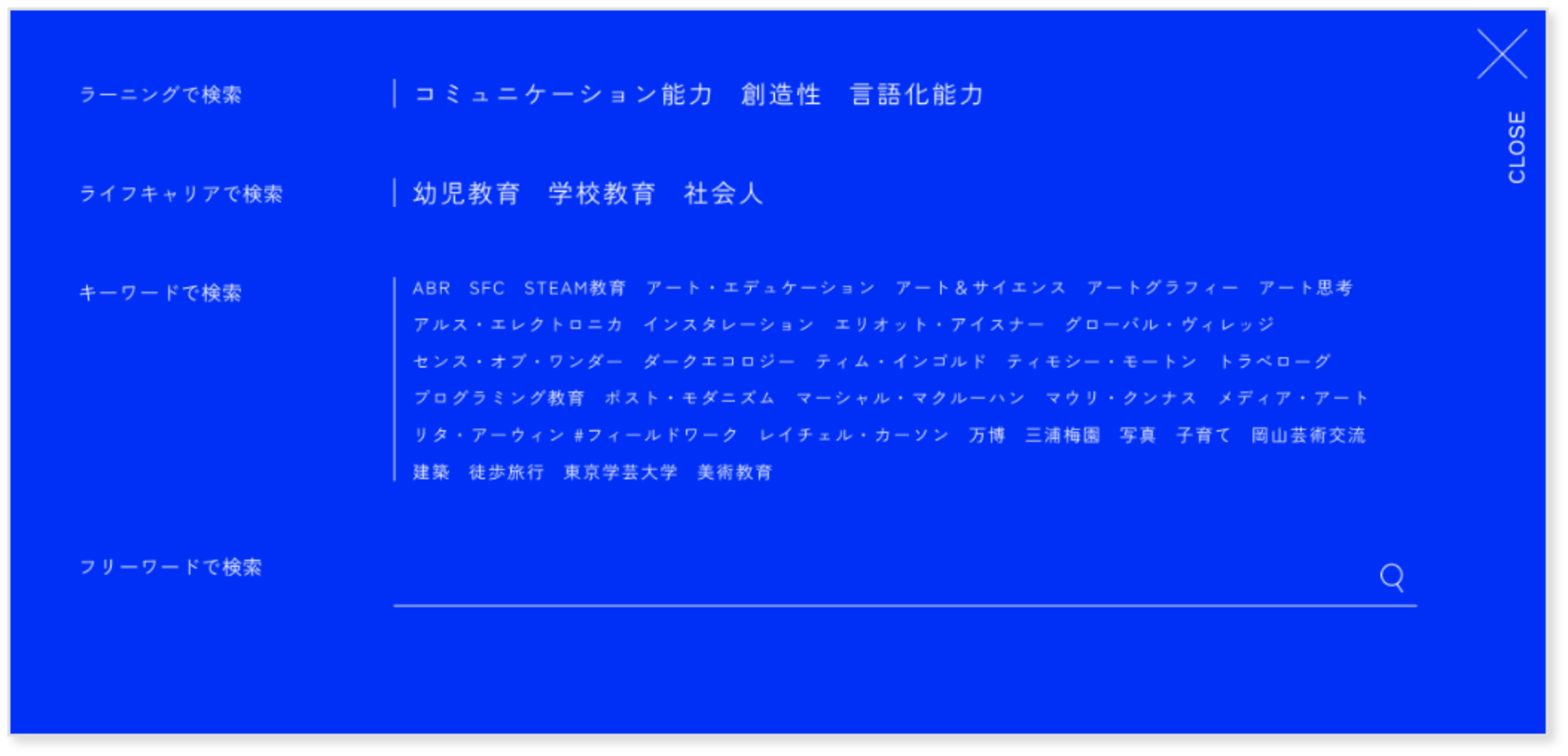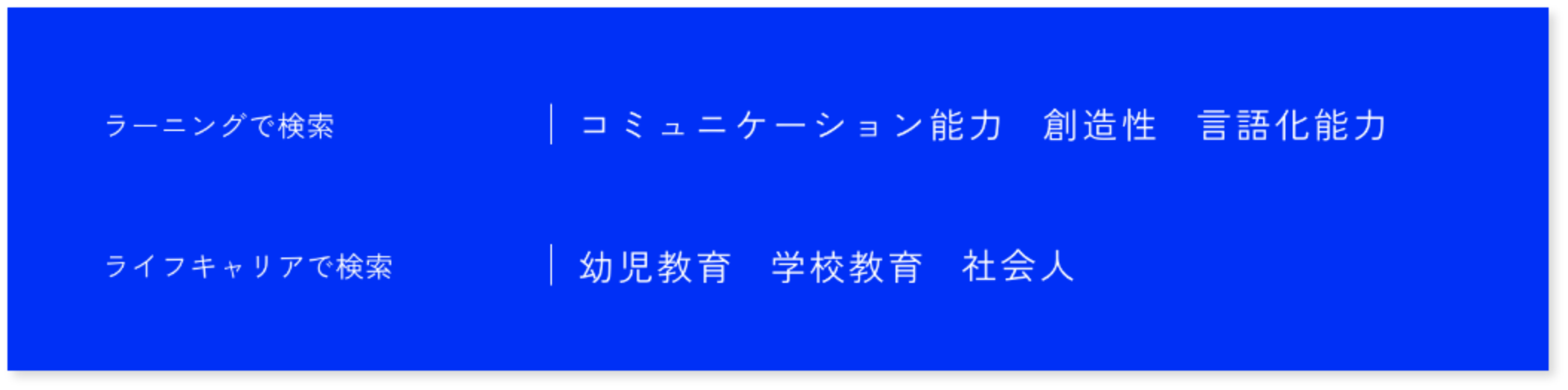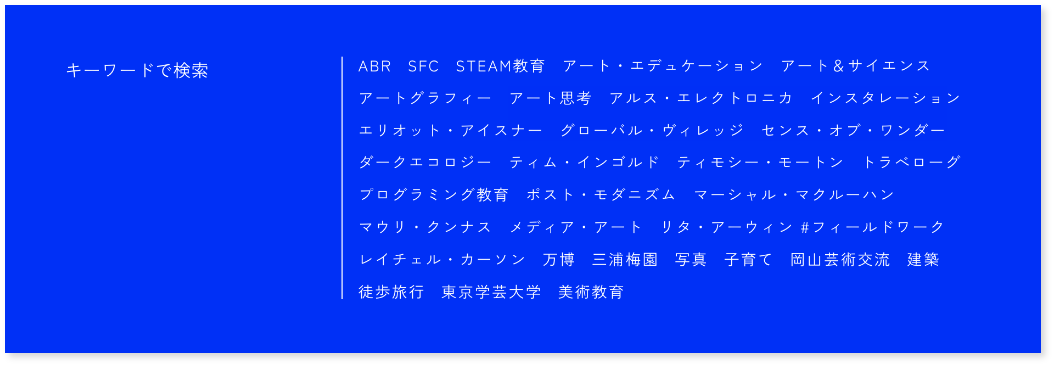千住だじゃれ音楽祭で野村誠が目指す“適度で中途半端”な表現
“自由に下手になる”即興演奏
地域の人がだじゃれを言い合うように気軽な気持ちで音楽を生み出していく「千住だじゃれ音楽祭」は、2011年のスタート以来、対面でのコミュニケーションが要になってきたのではないかと想像します。コロナ禍での近年はどのような活動をされていたのでしょう?
2020年以降3年間ほどコロナ禍で対面での活動がほぼできず、オンラインでの活動が主になりました。でも、オンラインのアプリケーションは音楽にあまり向いていないんですよね。楽器の音をノイズとしてミュートしてしまったり、話している人以外の音のバランスが小さくなってしまったりして。また、音楽をする際にはテンポを共有することが多いのですが、ネットのスピードの問題などで時間差が生じてしまうこともあって、その同時性が実現しづらいと感じました。
いっぽうで、物理的な距離を気にしなくていいので、オンラインでの国際交流を多く行いました。例えば、タイの音楽大学の学生とワークショップを行ったり、香港のお年寄りとのワークショップに参加したり、イギリスのコミュニティ・ミュージックのグループと交流したり。「世界だじゃれ音Line音楽祭」という名称でいろいろやりましたね。通常ならみんなで揃っていろんな国を訪れるのはなかなか難しいですけど、ネットになったことで逆にインターナショナルな活動の展開が増え、2021年には「アジアだじゃれ音Line音楽祭」と題してインドネシアやタイの人たちと交流もできました。

野村誠 千住だじゃれ音楽祭 presents 千住の1010人 from 2020年 「世界だじゃれ音Line音楽祭 Day1」
https://www.youtube.com/live/bYkwFoYyVQE?feature=share
オンラインだからこそのコミュニケーションが生まれるようになったのですね。
同じ空間にいる場合は、みんながほぼ同じ音楽を聞いているという前提がありますが、オンライン環境では、タイムラグによって聞こえる順序すら異なる可能性がありますよね。でも、そもそも“合っている”という認識は自分のものでしかない。本来はそういうもので、同じ音楽を聞いているつもりでも、実際には個々が異なる音楽を体験しているかもしれない。それでも、みんなが楽しんでいる。ズレのある不思議なコミュニケーションが生まれるものだな、と実感しました。
2022年頃からは対面での活動も再開しました。最初は換気や人数制限などの制約がありましたが、野外での演奏や船上での演奏など、さまざまな形で音楽を楽しむ機会をつくりました。また、千住の商店街でイベントも行ったのですが、踊る人もいるし演奏する人もいるし、誰が出演者で誰が観客なのかわからなくなるような、そんな場ができるようになってきました。
「だじゃれ音楽研究会」(通称“だじゃ研”)の在り方自体にも変化がありましたか?
最初は参加者側の立場だった人が、だんだんと研究会のメンバーになっていきました。2014年に“千住の1010人”という1010人による実験的な大合奏の企画運営の役割を担うようになったのがきっかけだと思います。その経験を通じて、即興演奏やコミュニケーションにおける、メンバー同士の関係性や演奏の質が変わっていったのではないかと思います。
それまでも即興演奏とは言っていましたが、セッション中のコミュニケーションは、もっと希薄でした。ある種、自分が外に向かうというか、人々に対して伝えていくという役割を持つ経験をしたことで、アマチュアとプロぐらいの違いが生まれてきたというか。即興が上手くなったんです。
即興演奏が上手いというのは、どういった状態を指すのでしょうか?
逆説的ではあるのですが、“自由に下手になれる”という感じ。洗練されていくというのは良さもあるけれど、不自由になっていくということでもあると思うんですよね。

「だじゃ研」の活動日の様子
正解を設定しないこと
先ほどの、オンラインで不思議なコミュニケーションが生まれたこと自体を楽しんでいるというお話と、即興演奏が上手くなったというお話は何か通底しているものがありそうですね。
即興の自由度が増していく過程を経て、だじゃ研のメンバー自身がファシリテーターなんだと思うようになってきたんですよ。僕が提供者ではなく、彼らが町の人にプログラムを提供する人なんだって。そして、だじゃれを交えた講座や、だじゃれ音楽の演奏、ゲストとだじゃ研メンバーによるコラボなどを結集したイベント「だじゃれ音楽研究大会」では、だじゃ研の人たちが自身の個性を活かしたプログラムを作成して、ワークショップなんかを企画するようになりました。ここには、洗練されたプログラムである必要はないという前提があるので、いい意味でくだらなく個性的で本当に面白いんです。そもそもコンセプトが「だじゃれ」なので気軽で自由なんですけど。そんなことを通じて、みなさんがパフォーマー兼ファシリテーターというか、一つのところに留まらないかたちで成長していくんですよね。
僕は人を育てるプログラムなんてやるつもりはなかったし、育てたつもりもないのですが(笑)、勝手に個性豊かな人材が育ってきたというか。不思議ですよね。2023年に入って、足立区を拠点とする「梅田クラブ」という、地域の高齢者が歌を歌ったり講座を受けたり、認知症予防を主な目的として活動している集まりがあって、ここで歌ったり踊ったりしながらみなさんとオペラのようなものをやったらどうかという動きも出て。“お客さん”としてだじゃ研のやっていることを単にデリバリーするのではなくて、元々あった土俵にどうやって関わって膨らませることができるのか……と、プログラムを自分たちで考えるようになっている。すごく頼もしいですよ。

高齢者による音楽サークル「梅田クラブ」での活動の様子
メンバーが能動的に動いていくための何か標語というか、あえて設定していることはありますか?
あらかじめ正解を設定していないということかもしれません。音楽とはこういうもので、こうであって、こうならなきゃいけない……という正解を設定していると、正解からずれているものを修正しようとしますよね。それで、そのために練習しましょうとかいうことになる。しかし、そうした正解を設定しなければ、お互いにやり合ったもの自体が、私たちの表現だったり交流だったりするのだと思うんです。
すると、このメンバーで集まって音を出すとどうなるだろう?とか、この環境に対してみんながアプローチすると、どういうものが出てくるだろう?出てきたものをどう楽しもう?という立ち位置ができてくる。こうならなきゃいけないみたいなイメージを持ちすぎないということですね。そういった意味では、すごく楽でもある。何かに近づけようと頑張る必要がなくて、出てきたものをこれはこれで面白いね、と。それって、人を否定しなくていいということにも繋がっていて、ストレスが少ないということでもあると思うんです。
メンバーである自分たちの心が解放される居場所が自然とできてくるということですね。
そうすると、他のコミュニティではすごく居心地が悪いと思う人も、「あ、ここだったら自分の居場所になるな」と思えることもあるのではないかなって。同調圧力が漂っていて息苦しいことってあるでしょう?でも、だじゃ研では、空気を読めとか、こうしなきゃいけないみたいなことを誰も言わないんです。いや、どうせみんなバラバラだから!みたいな(笑)。
野村さんの活動の中で、研究会の存在はすごく特徴的ですよね。音楽祭があったり美術の業界でも芸術祭があったり、お祭りなどのハレの場として何かをやるというのは比較的多いですが、ケというか、日常的なこととして活動するのは多くない印象があります。研究会を始めようと思ったきっかけはなんだったんでしょう。
東京藝術大学に千住キャンパスができて、2011年に「音まち千住の縁」という音をテーマにしたまちなかプロジェクトが始動した時に、「街に出るアートプロジェクトをやらないか?」という話が持ち上がりました。でも、もともと千住キャンパスは地元の小学校だった場所なのに、セキュリティカードをピッとやらないと入れないし、騒音対策でいつも窓は閉まっているし、外からは何をやっているのかわからない奇妙な建物に見えたんですよね。街の人々にとって、自分の通った小学校があった所なのに、これでは愛着も湧かないのではないかと感じました。いくら藝大の人たちが街に出てきて「何かやりましょう」と呼びかけたって、地元の人は入りにくいんじゃないかなと。
だから、この中に入る仕組みをつくりたかったんです。商店街や市場で何かを開催することを考えるよりも先に、藝大生でも教員でもない街の人たちががここに来られるという仕組み。それも、単にコンサートとか講演を見に来るとかではなく、みんなが何かするためにこの場所を訪れることができる環境をつくりたい、と。それが、だじゃ研を始めたことにつながっているんだと思います。
要するに、建物としての藝大というのは、いわゆるハイアート。実験的な音楽であろうとも、全て高尚な感じがしてしまうので、とにかくだじゃれをやりたいんですって。だから明確な意図をもって発足したというよりも、いつできたのかはっきりわからない研究会でもあって、いつの間にか生まれて、いつの間にかだじゃ研という呼び名になっていた(笑)。たぶん初期の時には、だじゃれ音楽ってなんだろう?みたいなことを研究する場が必要だろう、みたいなことを言っていたとは思うんですけれども。

千住だじゃれ音楽祭「千住の1010人」(2014年)の様子 写真=加藤健
https://youtu.be/8tWu43Hc3Ng
排除にブレーキをかける「駄」
アート業界ではよくホワイトキューブと呼ばれますが、ギャラリーの白い空間に厳かにアート作品をかけて鑑賞するのではなく、例えば街中で料理を一緒に食べるとか、一緒に絵を描くみたいなこともアートと呼ぼうといった活動があります。でもすごく対比的に扱われていて、高尚な芸術表現としてのアートから、日常の生活姿勢の表現みたいなものとしてのアートになったときに、何らかの翻訳が必要だなと感じています。
言語化が難しいですけど、排除にブレーキをかけるというか。排除にブレーキをかけるということは、そこで洗練されたものに対してズレが生じるもの。それが加わることで、より豊かになるというのが、僕の考え方です。ハイアートが低い(ロー)ところに下りて何かやってあげますではなくて、ハイアートに足りない部分を補うには「駄」が必要だと思う。そうすれば、場所を選ばない力強いものになっていくはずで。
日常に取り入れることで、変化は起きていますか。
例えば、音楽祭なんかはハレなふりをして、ケをやってるような部分もあるとは思うんですが、やっぱり、ハレがなければケは生かされないんですよね。ハレがあるからこそ人が集まる口実にもなるわけで、ケを継続することにもつながっている。だから、そこに向けて練習しよう、準備をしようということになるわけで、やはりハレは必要だと思う。
先ほど話した「千住の1010人」というイベントでは、本番を体験するためにいろんな準備をして、そこで人にどう伝えようみたいなことを模索しながらいろいろやった結果、また日常に戻ったときにその経験がすごく生かされるということが起きている。普段の仕事で会議の進行にすごく役に立っているとかいう人もいて。生かすつもりで始めたわけでもないのに、不思議ですよね。でも、1、2年やっていても出てこなかった効果みたいなものが、やっぱり10年くらい続けていると思わぬところで出てくるもの。ましてや音楽とは全然関係ないところで生かされているというのは面白いですよね。
即興音楽が上手くなるという先ほどのお話にもつながってくるようですね。
適度に人の音を聞き、適度に自分のやることにも集中するというか。普通は、自分は何を演奏しようとか、自分のことで頭がいっぱいになっちゃうものですが、そうすると人のことが見えなかったり、人の音が聞こえなかったりしますよね。かといって人のことばかり聞きすぎていたら、自分が何をしていいのかわからなくなる。だから、聞きすぎないけど、聞かなすぎるわけでもないという「駄」がやっぱり大事で、適度な中途半端さといえばいいでしょうか。その度合いはもちろん人によって違うものですが、その適度な中途半端さを、自分なりのバランスで楽しむことがすごくいいのかなと思っています。

「千住だじゃれ音楽祭」ディレクター・野村誠 写真=冨田了平
野村誠/Makoto Nomura
作曲家、千住だじゃれ音楽祭ディレクター。8歳で作曲を始める。中学時代は落語研究会に所属。1990年代より共同作曲を探求。ジャワ・ガムランと児童合唱のための《踊れ!ベートーヴェン》(1996)を発表以来、東南アジアとのコラボレーションを積極的に行う。野村幸弘との即興映像ドキュメントを行い、タイ(2004,2007)、インドネシア(2005)、カンボジア(2007)、台湾(2011)、マレーシア(2013,2015)など、約20本のドキュメンタリー映像を制作。日本相撲聞芸術作曲家協議会(JACSHA)理事。相撲から着想を得た作品を数多く発表。2014年から日本センチュリー交響楽団コミュニティ・ミュージック・ディレクター。オーケストラの可能性を拡張する試みを実践。淡路島アートセンターの委嘱で、やぶくみこと『瓦の音楽』を展開。2020年より、びわ湖・アーティスツ・みんぐる『ガチャ・コン音楽祭』ディレクターとして、サイトスペシフィックなプロジェクトを展開。著書に「音楽の未来を作曲する」(晶文社)などがある。