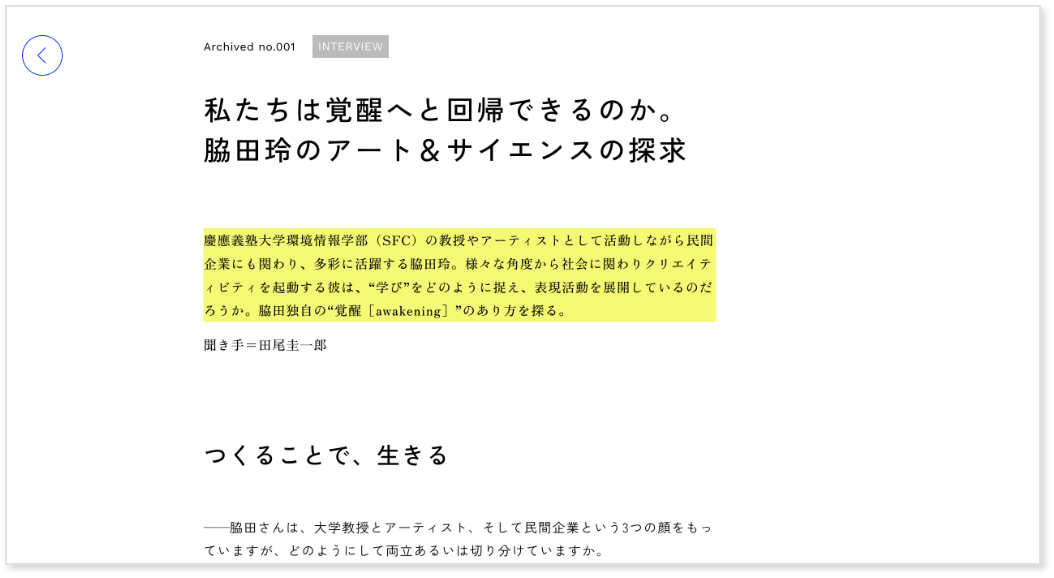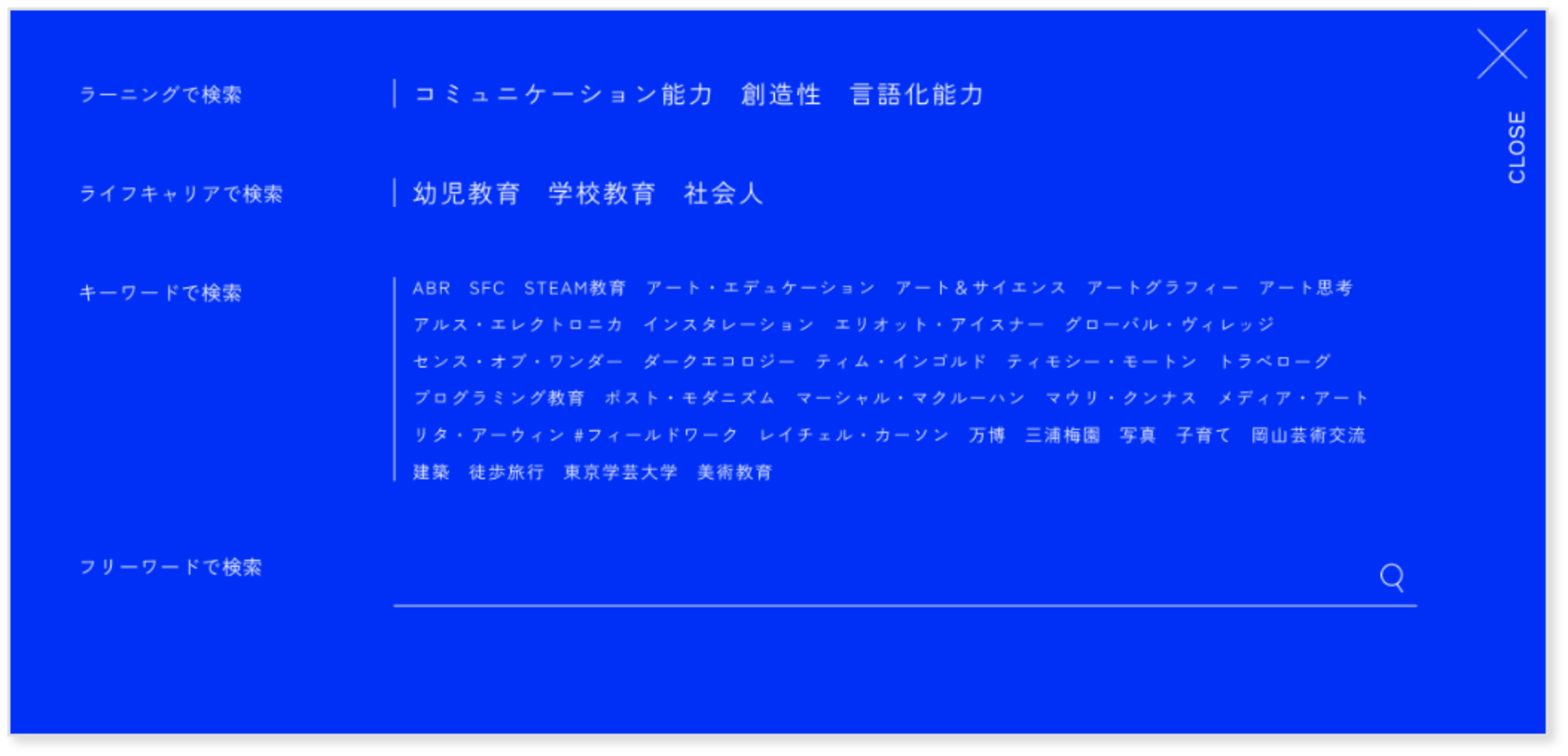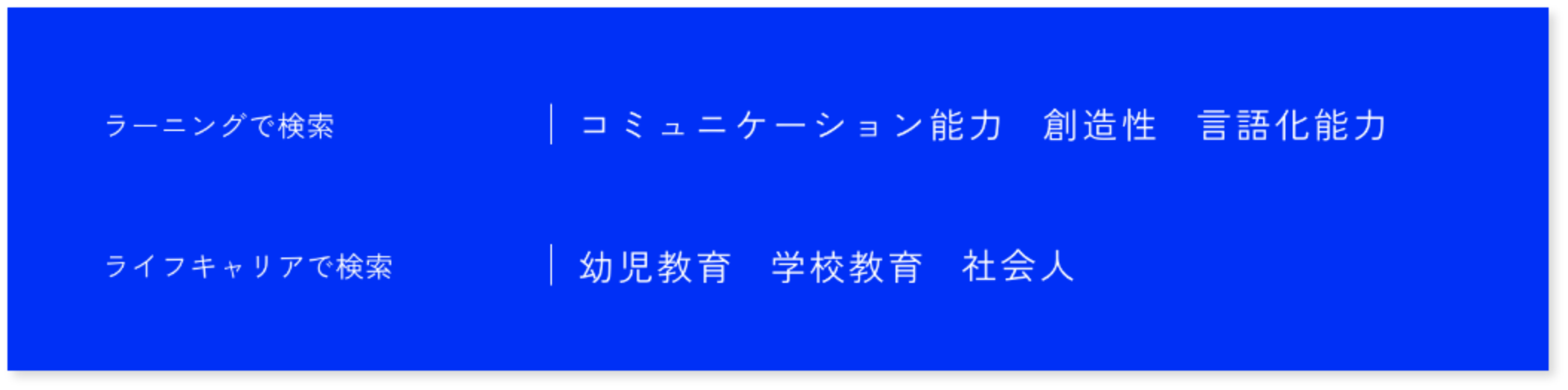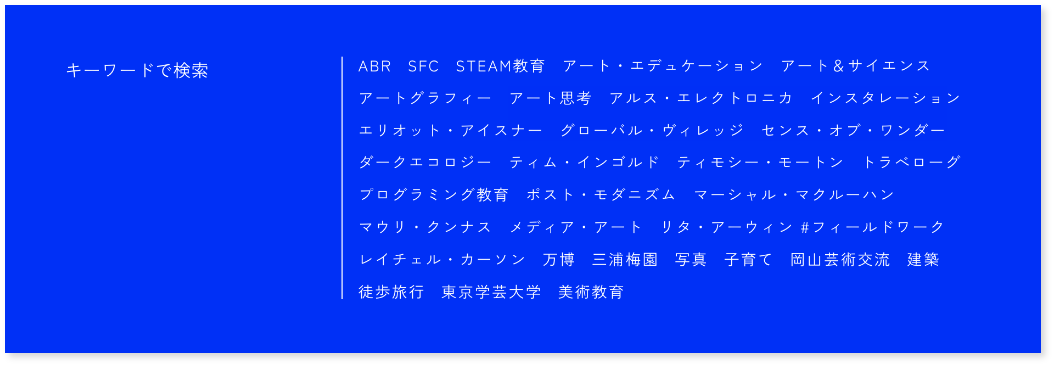世界をつなぎ直す、笠原広一の試み
表現・研究・教育をまたぐ「アートグラフィー」
アートグラフィーとは
笠原さんが編著書『アートグラフィー』(*1)で提言されている「アートグラフィー[a/r/tography]」は、芸術家[artist]・研究者[researcher]・教育者[teacher]の3つの実践の頭文字を表しており、スラッシュ「/」が示すようにそれらが完全に切り分けられない複数のアイディンティティや役割を持ちながら、探求していくアート・エデュケーションの理論・実践を指しています。この多様な自己を内包しながら学びと表現を深めていく姿勢は、現代社会において極めて重要な提案に思われます。
笠原 狭義のアートに限らない取組みであると同時に、探求者が自身のアイディンティティを深く掘り下げる、その人自身の「生きる探求」でもあるんです。表現方法は様々で、プロジェクト毎に異なるのはもちろん、同じテーマでも人によって表現手段も文章やビジュアル、演劇と様々です。ただ思いを言葉や絵に置き換えるのではなく、可視化することでその意味が何なのか、その先を考えることを「アートグラフィー」では重要視しています。
探求のあり方に応じて様々な表現方法を用いることも多いため、普段は油絵を描いたり彫刻をつくったりしている学生がこのような授業に参加すると、戸惑ってしまうことがあります。しかし、本来、表現方法は限定されるべきものではないですし、もちろん新しいものにチャレンジしてもよい。そもそも自分の表現したいものや考え自体も変化するし、明確でない場合さえあります。アートグラフィーを実践することで、自分の新たな感覚や自己理解が立ち上がっていく。自身と社会、世界の関係をrelate(関連づけて)していくそんな作法のようなものなのです。
例えば好きな人と夏休みに花火大会に行ったときのことを想像してみてください。そこで感じた「夏の夜の暑さ」とは単に気温や湿度を意味するわけではなく、二人の感情が多分に含まれたものになるのではないでしょうか。それに対して、相手が気温や湿度を数字で真顔で語ったとしたら、たぶん暑さの意味からも相手の気持ちからもズレてしまうかもしれません。このとき問題は科学というよりも、気持ちや文脈など、詩や小説、写真や映画などアートの領域にあるわけです。そのため、共にいることで感じた暑さを言葉やビジュアルでアートとして表現してみようとすることが、こうした領域のコミュニケーションと人生を豊かにしてくれます。アートが生み出す“智”が人間には必要なんです。
そのうえで美術教育は、図画工作や美術をする場合であっても、私たちが人生を生きていくうえで自分のあり方を見つめ直したりできるような活動をもっと行なっていく必要があると思います。「自分は別に将来絵を描かないから美術なんて関係ない」ではなく、美術教育で得た表現力や育んだ感受性を自分(たち)のために用いたり、様々な形で社会に実装していくことが必要なのではないでしょうか。学校だけでなく社会と紐付き、いろいろなものを生み出しながら学びや成長を得る。そのためにアートグラフィーは、「自分の表現したいことを作品にする」のではなく、目的さえも曖昧に「何を問うのかも含めて考えて表現する」ことや、「表現する中で気づいていく」ことを体験させてくれるのです。
日本の美術教育をどのようにアップデートするか
笠原さんがアートグラフィーに可能性を見出されたのは、どのような経緯だったのでしょうか。
笠原 プロジェクトが始まったのは2014年頃でしたが、本格的にスタートしたのは2016年頃、僕が東京学芸大学に来てからです。最初のきっかけは、2011年頃に博士論文を書き始めた頃でした。アートグラフィーやABR[Arts-Based Research] (*2)について海外の文献で知り、衝撃を受けたんです。自分ももともと学芸員でしたし、京都の美術大学で仕事をしたり、国民文化祭のアートプロジェクトを企画したりもしていましたが、そこで経験してきたこととアートグラフィーの提示しようとしているものは、世界観が、大きく異なっていました。
海外では当時からアートグラフィーについての議論がされていたのですか。
笠原 海外では1990年代からアートと人間の可能性について、美術教育はもちろん、様々な学問領域の間で問われ続けていました。ポストモダニズム(*3)が議論され、経済成長に社会が向いていた当時の日本とは実に対照的です。具体的な先駆者を挙げるとしたら、例えばアメリカの教育学者エリオット・アイスナー(*4)がいます。「人間には多面的な側面があり、必ずしもペーパーテストで測るような知識だけではない」と述べ、芸術は人間に対して智を拓き得るとしました。90年代に入ってからアイスナーは、ABR(Arts-Based Research)を通して文学やアートが具体的にどのような智を生み出すのか、ということを研究するようになります。そして現在では、『アートグラフィー』の共著者でもあるリタ・アーウィンらがこのジャンルの研究を引っ張っています。
当時の日本の美術教育は、描くことやつくる表現の技術に意識が向けられがちでしたので(現在でもそうした傾向はありますが)、教育の文脈で子供たちと行う活動という点で大きな違いはありますが、展覧会や批評で議論される“アート”とはどうしても議論が離れたものになりがちでした。もちろん、なんでも一緒に考えればいいとは思いませんが、それらをつなげる試みでもあったアートグラフィーやABRについても、日本には研究するフィールドがありませんでした。
そんななか、海外の学会でアートグラフィーの提唱者でカナダの教育学者でもあるリタ・アーウィンに会い、一緒にプロジェクトを行うことになりました。以降、一緒に論文を読んだりプロジェクトを行ったりするようになり、今回の書籍出版の話になったのです。
歩くことを通した
アートグラフィックな探求「東京ウォーキング」
ぜひアートグラフィーの具体例についても教えてください。2018年に「マッピング・アートグラフィー」という東京を練り歩くプロジェクトを笠原さんは行われています。これはどのようなものなのでしょうか。
笠原 国内外から集まった人々が東京を歩くことで、何を感じ、考え、問い、見出していくのか。その探求を、造形や言葉、パフォーマンスやワークショップなどで表現し問いを深め、地図にプロットすることで、新たな対話や気づきを見出そうという試みです。上野公園、代々木公園、下北沢、昭和記念公園、新宿御苑などを歩き、アートグラフィーとしての探求を深めていきました。
公園などを歩くことでフィールドワーク[Research]し、それを各々のかたちで表現[Art]し、最後にマッピングすることで可視化[Teach]しているのですね。なぜ、「歩く」ことに重点が置かれたのでしょうか。
笠原 いくつか理由が挙げられると思いますが、ひとつはリタ先生たちと「歩く」という行為を探索的な方法として捉えていたためです。「歩く」ことは人間にとって原初的な探求の方法論ですし、パフォーマンスとしての表現方法のひとつとしても見ることもできます。メンバーと一緒に歩くことで、何か共鳴し合うものがあるのではないかと思ったからです。リモートでの打合せが日常化した昨今、歩くことについて身体的に感じることが少なくなってきています。だからこそ、こうした身体性を直接的に感じられる「歩く」ことを企画に取り入れれば、得るものも多いのではないかと思いました。アートグラフィーとして歩くことによって、自分の感覚が立ち上がり、世界との関係性を気づき直すことができるのです。この場合のリサーチとは、フィールドワークで歩くことはもちろんですが、表現や様々な対話も含め、その探求過程全体もまた、リサーチ(探求)でもあるのです。
ティム・インゴルド(*5)が「徒歩旅行(*6)」を唱えているように、歩くことで観察できるもの、表現できるもの、そして共有できるものは少なくありません。プロジェクトの結果はどうだったのでしょうか。
笠原 メンバーの中には、東京生まれ東京育ちの学生もいれば地方出身で上京してきた学生、はたまた中国からの留学生もいて、東京との関わりが多様な状態でした。みんなそれぞれ歩きたいところを歩いて、そこで考えたことが何なのかを振り返ったときに、学生が「歩いて表現したものを集めて、展覧会をやりたい」と言ったんです。「歩いてエッセイを書けば授業は終わり」と言われてもピンとこない、と。そこで、各々が感じたモヤモヤや気づきを話して、展示というかたちにしました(図1)。こうした探求はもはや課題というよりも、学生たちが自分自身を捉え直す取組みにもなっていたのです。

図1 大学のギャラリーで行われた展示の様子から 撮影:笠原広一
学生がResearchだけでなくArtやTeachの要素を主体的に行なったということですね。アートグラフィーの3要素が相互に補完し合っていることを感じる取り組みです。
笠原 2018年にはsomatic awareness[身体的な気付き]からより長時間にわたるjourney[旅]としてアートグラフィーを行うべく、熊野古道を複数日にわたって歩き、“travelog[travel+log、トラべローグ]”として道中記をつけるプロジェクトも行いました。“お遍路さん”など、日本人はときに歩くことを人生に重ねますが、熊野古道という歴史的・文化的な場所を歩くことで、より継続的な試みとして世界との関係性をつなげる活動に挑戦しました(図2)。

図2 熊野古道を歩く道中での一枚 撮影:笠原広一
現在、アートグラフィーは大学の講義として設けられているのでしょうか。
笠原 2018年から2020年まで中央大学文学部の授業として15回ほどABRやアートグラフィーの授業を行いました。しかし私の所属している東京学芸大学では、ABRやアートグラフィーの授業そのものはカリキュラムとしてはありません。複数コマを用意しないといけないので、オムニバス形式で3回授業を行ったり、大学院の集中講義で6回分行ったり、特別枠として実施することが多いです。大学以外では、社会人や現職の先生向けあるいは学会向けにエッセンスを体験できる3時間程度のプログラムを開いたことはあります。対企業では、アメリカンアパレルブランドGapの店舗と協力し、顧客イベントの一環として親子の制作体験を行ったりもしていますが、今後はそのエッセンスをもとに、こうした社会の様々な場所で展開していけたらと思っています。
学生たちには将来的に教員になるにせよそうでないにせよ、アートを通して人と一緒に何かを具体化する経験をしてほしいし、できればそのことを研究してほしいとも思います。「研究と教育現場は関係ない」と言われることもありますが、実践と研究を行ったり来たりしながら、アートグラフィーを社会に実装させていきたいです。
海外のアートグラフィー事情
笠原さんは、海外の研究者とも協働されていますね。
笠原 オーストラリアや韓国とは長く共同研究をしています。メルボルンの大学とは、日本とオーストラリアが共有する太平洋を踏まえて、マイクロプラスチックや環境について一緒に考えるというワークショップをしました。また韓国とは、2021年から2年間ほど、日韓の異文化理解をテーマにしたABRに関連するプロジェクトも行いました。特に歴史認識においては、直線的にタイムラインをlook back[振り返る]するだけでなく、過去と現在を意味づけし直し未来をlook forward[展望する]ことが重要です。可視化しきれていない感情やモヤモヤを、当事者が表現する術を持つこともアートグラフィーの特徴です。両国の学生たちが就職など社会で働くときに、こうした経験によって相互の関係が好転していけばよいなと思っていますし、こうした取組みをさまざまな国や地域の人々との間でつなげていってほしいと思います。
このように、教育やアート以外の分野でもアートグラフィーは有効です。今後も3割ぐらいは、海外との協働をやっていきたいと思っています。
今後、若い世代がアートグラフィーをどう利用していくべきか、笠原さんの展望を教えてください。
笠原 アートグラフィーの大事なところは、当事者がリサーチし、表現する術を持ち、自らについて語り、人とシェアする──ということが可能な点です。そうしたことを包括的に行うひとつのフレームなんです。どちらかというと、ABRを実践するのはアーティストやリサーチャーが多いと思いますが、アートグラフィーは誰もが語りの当事者になり得ます。そういう意味ではまだまだ未知の可能性があると思っています。
現段階では、ABRやアートグラフィーを学校教育関係者に紹介すると、「学校教育とかけ離れている」というリアクションが返ってくることもあります。しかし、アートグラフィーのエッセンスがうまく伝わって、それぞれの現場や子どもたちの実態に合った形と内容で実践されて広がっていけば、もっと様々な人に取り組んでもらえるはずです。
アートは自己理解を促します。自画像を描くことを通じて自己に向き合うという方法もありますが、多面的で複雑な関係性と深度をもった自己について問い深め、探求を通して新たな自己をも創っていく営みとして、アートグラフィーには大きな可能性があると思っています。そもそも美術教育研究は、効果や意味が不明瞭になりやすいので、その有効性を伝えようとすると難しいところもあります。しかし、だからこその面白さを若い学生には伝え、実際に取組んでもらい、次につなげてもらいたいなと思います。

笠原 広一 (かさはら こういち)
東京学芸大学 教育学部准教授(美術教育学)。チルドレンズ・ミュージアムでのワークショップや展覧会企画、芸術系大学附属の幼児教育施設での美術教育、教員養成大学を経て現職。美術教育が専門で,アート・ワークショップ、幼児の美術教育、a/r/tography(アートグラフィー)やArts-Based Research(アート・ベースド・リサーチ:ABR)の研究に取り組んでいるほか、地域の文化事業の企画コーディネートなどにも携わる。
主な著書に『アートグラフィー』(2022年、学術研究出版、共著)のほか、単著『子どものワークショップと体験理解』(2017年、九州大学出版会)、『まちと・アートと・場づくりと』(2022年、学術研究出版 )などがある。
『アートグラフィー −芸術家/研究者/教育者として生きる探求の技法−』
アートグラフィー(a/r/tography)は、カナダの美術教育研究者リタ・L・アーウィンが提唱する、アートとリサーチと教育への関わりを通した「生きる探求」の技法/理論である。A/r/tは、アートに加え芸術家(Artist)/研究者(Researcher)/教育者(Teacher)を意味し、多面的アイデンティティの混淆を表す。さらにA/r/tに“graphy"(記述)が加わり、アートベースのハイブリッドな探求技法となる。自己と社会の“あいだ"にアート/リサーチ/教育を通して新たな可能性を模索する人々に送る一冊。