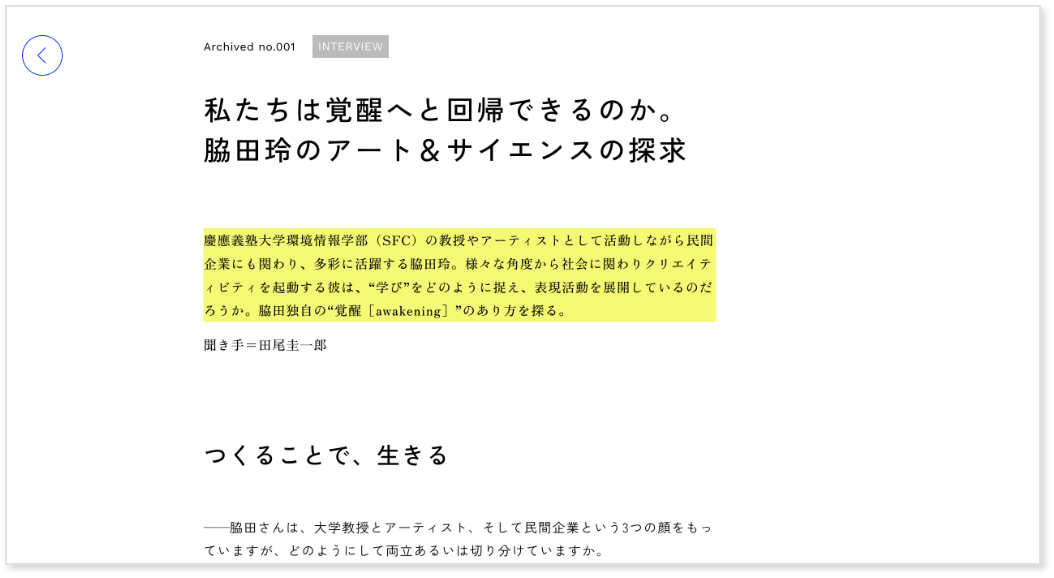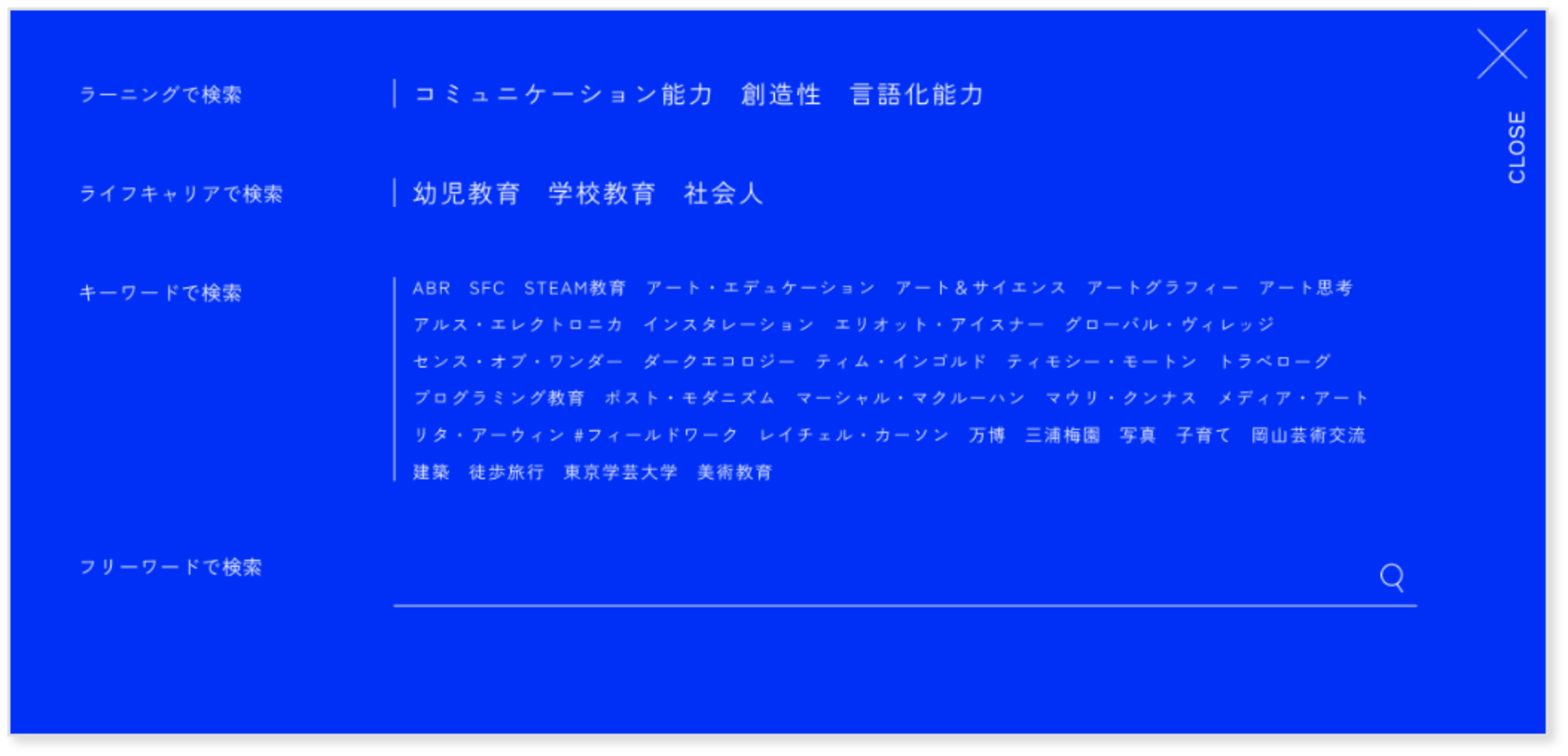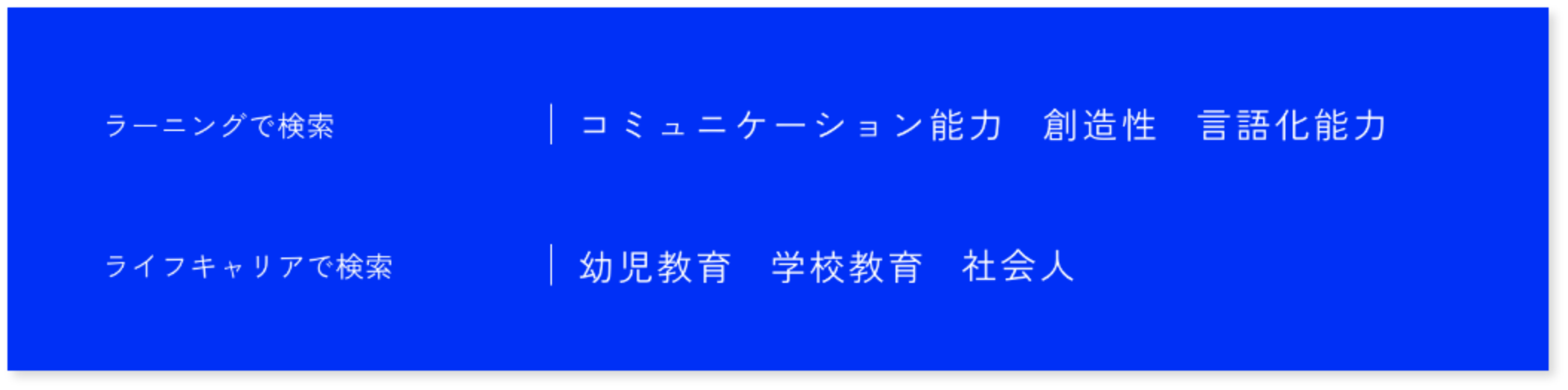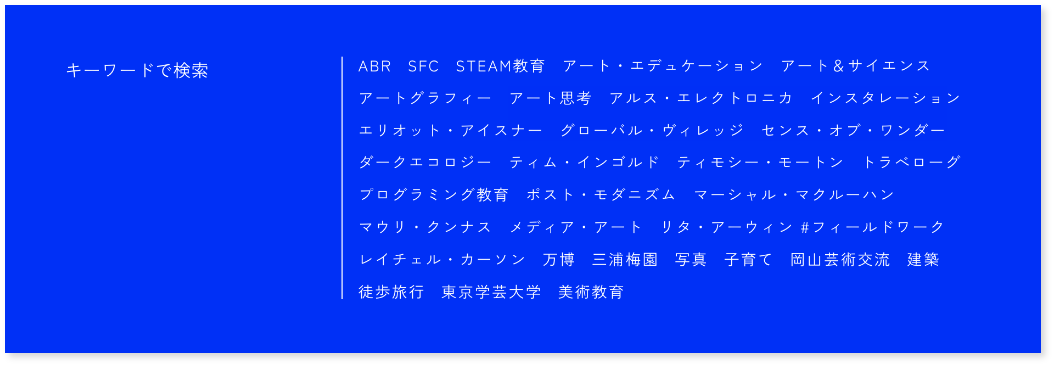私たちは覚醒へと回帰できるのか。
脇田玲のアート&サイエンスの探求
つくることで、生きる
脇田さんは、大学教授とアーティスト、そして民間企業という3つの顔をもっていますが、どのようにして両立あるいは切り分けていますか。
脇田玲(以下脇田) これらに共通する私のスタンスは、「ゴールを明確に設定しない」ということです。40歳を過ぎたあたりから、目標に向かって頑張るという生き方を考え直しまして、「5年後にこんな社会を実現したいから、今これをやらねば」と、綿密な計画を立ててマネジメントをすることもまったくありません。この10年間は漂流者のように気づいたらこうなっていた、という感じです。もちろん、その時々は必死にあがいているんですけど、あがいても思うようにはいかないですよね。振り返ると、私が関わっている会社名「INERTIA」(*1)の語源にもある通り“カンセイ(慣性/感性)”に任せて行き着くところに行き着いているんです。
そういったスタンスはこれまでのキャリアのなかで、どのように形成されていったのでしょうか。
脇田 特に大学との関わり方は年齢によって変わってきています。私は29歳で慶應義塾大学に有期教員として雇用されました。雇用契約が有期でしたので、とにかくサバイブすること(=大学で専任教員としてのポジションを得ること)を重視していました。 なので、雑用を全部引き受けて、授業も山ほどこなして、寸暇を惜しんで論文を書くという、いわゆる真っ当な研究者でしたね。そういう生活を何年か続けて運良くテニュア(終身在職権)を得てからは、上司や組織のための研究ではなく、自分の研究成果を出すことを第一に考えるようになりました。著名な学会に論文を通したいと考えて努力はするも、連戦連敗が続く。そんな30代でしたね。
研究者としてのあるべき姿から解放されて「これからは好きなことをしよう」と考え方が変わったのは、39歳のときに大きな病気をしてからです。その直前に教授に昇任して雑用などの制約が少なくなったこともあり、自然にそういうスタンスになっていきました。
アーティストとしての活動も、その頃から始まりましたよね。
脇田 そうですね。とにかくつくりたいものをつくる。いま振り返ると、死を意識してたのかなと思います。“つくる≒生きる”という感覚で、生き残るために、もしくは納得して死ぬために何をするか。(《Vortex》(*2)でモチーフにした)縄文人も同じような意識を持っていたのかもしれません。旧石器時代の日本で膨大な土器がつくられたのは、苛烈な環境の中で生き残るための祈りのようなものであったという説があるそうです。
いま、40代後半になって思うことは、未来を考えれば考えるほど、やっぱり“人”に行き着くということです。若い人と接して、彼らに何を残せるか、そして彼らから何を吸収できるか。“人”にフォーカスするようになりましたね。

脇田玲 Vortex リアルタイム・ソフトウェア、縄文土器 2022年
真理への覚醒
自身の感覚に従って生きていくとき、自覚のあるなしに関わらず人は選択の判断軸を持っているはずです。脇田さんはどのように判別していると認識されていますか。
脇田 自分の心が動かされるかどうかを大事にしています。「偉い人がこれが良いと言っている」とか「いまこれが新しい」だとか、そういうことは気にしない。例えば、NFTは可能性に溢れる技術だと思いますが、私はあまり興味がないですし、心が動かないんですよね。いっぽうで違和感にもとづいて選択するときもあります。特に、勧めてくれた相手が私の心を動かすようなクリエーションをしている人の場合は、違和感を感じても積極的に選択して、やってみるようにしています。
クリエイティブ・ディレクターやプロデューサーといった職種を筆頭に、複数の分野にまたがって活躍する方はいらっしゃいますが、その多くが俯瞰する力や翻訳能力が高い人です。昨今注目される“学際性”のある人も、そういったスキルが優れていることが多い印象です。いっぽうで脇田さんは、大学教授やアーティストのような探究していく専門性の高い職種でまたがっている。
脇田 私は不器用なので、原初的な心の動きが重要ですね。興味の対象も感受性も狭いタイプです。みんなが10見ているのに私は1しか見えてないんじゃないかと思うことがよくあります。クリエイティブなディレクションをする人は、センサーの広い方が多いですよね。様々な情報を持っているから“良い/悪い”の決定ができるんだなと思います。私の場合はそれがなぜ良いのかを説得するだけの知識の幅がないので、比較や判断をすることができない。だから必然的に自分に見えている1つか2つのものと向き合っていくうちに専門性が上がっていくのかもしれません。
“狭い/広い”といった二極化された知覚ではなく、異なる世界認識があること、複層的な知覚の可能性を、脇田さんの作品は問うてると思っています。それがどのようなオリジンを持つのか、少しちがう角度からも探らせてください。脇田さんは、教授・アーティストのいずれでもない、プライベートの時間はどのように過ごされていますか?
脇田 車で地方に行って自然の中に身を置いていることが多いですね。ずっと波を見るとか、太陽を見るとか、浜辺で流木を見つけて削り続けたりとか、そういう感覚的なことばかりしています。あとは犬と一緒に遊ぶぐらいです。読書することもありますが、書籍をいくら読んでも行きつけない種類の“知”があると勝手に信じています。現代アートが扱っているのはそのような種類の“知”だと思っていて、現代科学がつくり出した難解な概念や数式を腹落ちしてわかったと感じるのにも、同様の“知”が求められると思っています。それを得るには、自然の中に身を置いて、異質な概念を腑に落ちて解るための身体的なスキーマを全力で鍛えることだと思っています。その意味で、データの海やコードの森、情報の自然といったものに身を置くことも重視していて、プログラミングは今でも意識して使うようにしています。
これまでの作品を拝見していると、空気の気配を可視化した《Ryoanji / Parking》や自然と一体化を図る《Triplet》など、メディア・アートでありながら自然や現象がモチーフになっている作品も多いですね。
脇田 私は人間がつくるものは取るに足らないものと思っているんです。レイチェル・カーソンが『センス・オブ・ワンダー』(*3)の中で「くだらない人工物から距離をおく」ことの重要性を言っているのですが、そこはすごく意識していますね。新しいテクノロジーや偉い人がつくった作品に触れるよりも、蕾を見ているほうが学ぶことが多い。当たり前のものとして認識しているもののなかに、すごいことが潜んでいて、それを常に探しています。自分自身が作品としてくだらない人工物をつくりながらも、自然のスーパーパワーに少しでも近づきたい、少しでもそれを自分で明らかにしたいという気持ちがあるんです。
自然を観察することでその真理に近づくことができる、ということでしょうか。
かつて縄文人は持っていたのに現代人が使わないせいで錆びついてしまったセンサーはたくさんあると思います。江戸時代の自然哲学者・三浦梅園(*4)の言葉で、「枯れ木に花咲きたりというとも、先ず生木に花さく故をたずぬべし(*5)」というのがあります。枯れた木に花が咲くのは、手品だったりテクノロジーだったり何かしら人工的なものが介在しているからですよね。そんなことに驚くよりも、毎年桜の花が咲いて散っていくことこそが驚くべきことだと説いています。そういう三浦梅園的センサーは環境を変えれば復活できると思っているんです。だから新しい技術や思想、トレンドにそこまで興味がないんでしょうね。
そういうお話を踏まえて昨今のメディア・アートを振り返ると、テクノロジーの新しさのみに答えや表現の可能性を追い求めるのは近視眼的すぎるかもしれません。
脇田 メディア・アートは基本的には新しい技術と向き合う行為だと思っています。だから私は、自分のことはメディア・アーティストではなく、むしろ画家に近い立場だと感じています。私が好んで使う“アート&サイエンス”という言葉には、狭義と広義の意味があります。狭い意味ではそのままジャンルとしてのアートとサイエンスを指しますが、広義でいわれる“サイエンス”は普遍性に基づいて世界を見るという意味なんですよね。いっぽうで“アート”は、人間が手でつくるもの、人間の直感や洞察力によってつくるものを指します。つまり、自らの特異性から世界を見ることです。両方を併せ思考しながら、どこまで世界の見方を更新していけるか。そして、普遍的だと思っているものも、実はずっとそれが正しいわけではなく、日々ダイナミックにつくり直されいることを忘れてはなりません。そういう動的な流れの中に我々は身を置いているんです。だから、誰かが見つけて整えてくれた普遍性だけ享受していても、世界はあんまり面白くならない。
世界をどう知覚し、拡張していけるか。脇田さんが持つ様々な顔に共通しているのはそういった姿勢なのでしょうか。
脇田 (技術などの)拡張[augmentation]ではなく、覚醒[awakening]です。人間の可能性を広げるのではなく、根源に迫っていくほうに関心があります。そもそも人間は本質的に成長できるのか、という問いですね。

脇田玲 Triplet 8K / ビジュアル・オーディオ・インスタレーション 2020年
自然としてのアート&サイエンス
2000年前後に生まれた世代にとって、デジタルは物心ついた頃からあり身近な存在です。彼らにとっての“自然”や“覚醒”は何に立脚していくのでしょうか。
脇田 若い人と“自然”に関しての議論はあまりしたことがないですが、彼らはティモシー・モートンの「ダークエコロジー(*6)」に近い感覚を持っていると思います。人間がつくってきたデジタルもくだらない人工物も全部含めて、“自然”だと。そこに良いも悪いもなくすべてをエコロジーとして受け入れる感覚が、私の世代よりちょっと強い印象があります。その環世界の中で自在に動ける力は獲得しているのではないでしょうか。彼らがもう少し成熟してきたときに、その本質に対して何かしら意識し始めるはずです。
私の世代は、ちょうど大学に入る頃にインターネット・カルチャーが台頭しまいた。規制もほとんどなく、理想的な世界だったように思います。それが徐々に、社会学者のマーシャル・マクルーハンが「グローバル・ヴィレッジ(*7)」と指摘した通り、危険なインターフェイスとして成長したウェブを目の当たりにするようになりました。デジタル以前と以後という感覚が強く残っており、今の若者のようにあるがままのエコロジーとして全体を受け止めることができずにいる世代だと思います。
20代の方から見たメディア・アートと脇田さんから見たメディア・アートは、受け止め方としてどのようなちがいがあるでしょうか。大学教授として日頃学生と接するなかで、どう思われますか。
脇田 彼らはいわゆる“デジタル・ネイティブ”なので、メディア・アートが問題にしているメディア論とか身体の拡張についてはあまり意識していないように見えます。1990年代の日本のメディア・アートの出現を経験した人たちは、現在のあり方、つまり企業のマーケティングを助長する手段のようなあり方には疑問を持っていることでしょう。一方で、若者たちは、日常的に消費するものとしてとらえているのではないでしょうか。アルス・エレクトロニカは「蛇口をひねると未来が出てくる」(*8)と言っていますが、若い人も似たような感覚を持っていると思います。未来まで見据えている若者は残念ながら僅かですが、多くの若者は水や電気、パケットと同じような消費する対象として、メディア・アートを見ている。ある意味、作品の背景にある思いや作家性よりも、表象や技術を重視している。そういう無機質でニュートラルなものとしてアートが消費されているように見えます。
そのような若い世代に期待することはどんなことでしょうか。
脇田 アーティストの心を持ったサイエンティスト、サイエンティストの心を持ったアーティストが増えていくことを期待しています。今日のアート業界ではヒューマニティの視点でアートの批評がなされることが一般的ですよね。しかし、一見無関係のように見えるかもしれませんが、サイエンスの心をもったキュレーターや美術家がもう少し増えれば、アートを通した人間性の理解はより深まっていく気がするのです。
サイエンスの世界についても同様のことが言えます。サイエンスがサイエンスであり続ける限り、大事なことはいつまで経っても明らかにならないのではないでしょうか。アーティストの心を持ったサイエンティストが増えていけば、細分化とは異なる種類の世界の理解が深まっていくと信じています。DXやプログラミング教育というシフトであったり、専門教育からSTEAMへのシフトといったものは、そのような未来と繋がっているはずです。

脇田玲(わきた あきら)
科学と現代美術を横断するアーティストとして、映像、インスタレーション、パフォーマンス等を展開している。Ars Electronica Center, WRO Art Center, Mutek, 清春芸術村, 日本科学未来館, Media Ambition Tokyo, 21_21 DESIGN SIGHTなどで作品を発表。主な展示に「アランとキースのために」-中村キース・ヘリング美術館(Hokuto Art Program ed.1)(2022)、「高橋コレクション『顔と抽象』-清春白樺美術館コレクションとともに」(2018)、日産LEAFと一体化した映像作品「NEW SYNERGETICS -NISSAN LEAF X AKIRA WAKITA」(2017)などがある。
http://akirawakita.com